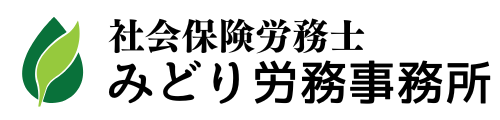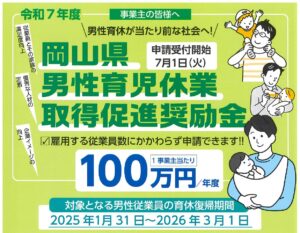介護人材の確保へ専門委員会が始動 2040年を見据え
介護現場の深刻な人材不足に対応するため、「第1回 福祉人材確保専門委員会」が開催され、本格的な議論がスタートしました。厚生労働省は2040年を見据えた体制構築を急いでおり、私たち社会保険労務士にとっても、制度と現場をつなぐ“橋渡し役”がより重要になってきます。
■ 将来の人材ニーズと現状のギャップ
2024年から始まる第9期介護保険事業計画では、2026年度に必要とされる介護職員数は約240万人、さらに2040年度には約272万人に達すると見込まれています。しかし、現在の介護職員数はおよそ215万人。今後も人材不足の状態が続くと予測されています。
こうした現状を受けて、厚生労働省では「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会を立ち上げ、持続可能な介護体制の構築に向けた検討を進めています。
■ 中間まとめに示された主な課題と論点
2024年4月10日に公表された中間とりまとめでは、以下のようなテーマが重点的に示されています。
- 地域の特性に応じたサービス提供体制の見直し
- 中山間地域では、需要の減少にあわせたサービス基盤の整備
- 都市部では急増するニーズに対応するための新しいサービスモデルの導入
- その他の地域では、需要変化に対応した柔軟な体制づくり
- 介護職の人材確保と職場環境の改善、生産性の向上
- 地域包括ケアの強化と医療・介護の連携体制の整備
■ 専門委員会での主な議論の柱
今回の専門委員会では、上記の課題を踏まえ、以下の4つのテーマを軸に具体策が議論されます。
① 地域ごとの人材確保の進め方
地域の実情に即した課題を明らかにし、ハローワークや福祉人材センター、教育機関、事業者などが連携して解決に取り組む仕組みが求められます。
② 多様な人材の参入促進
若年層や高齢者、介護未経験者など、幅広い人材層の活用と、業務の見直し・切り出しによる柔軟な働き方の導入も視野に入っています。
③ 中核的な介護人材の育成
介護福祉士を中心とした教育体制や資格取得のあり方、キャリアパスの明確化などが検討されます。また、潜在的な有資格者の再就職支援も重要なテーマです。
④ 外国人介護人材の受け入れと定着支援
小規模事業所でも外国人材を受け入れやすくするために、地方自治体のサポート体制や日本語学習の支援が鍵となります。
■ 今後の予定
今後は、夏にかけて関係者へのヒアリングや委員会での議論が進められ、秋頃には具体的な提言が取りまとめられる予定です。
介護現場の持続可能性を高めるためには、制度面だけでなく、私たち一人ひとりの理解と協力も欠かせません。今後の議論の行方に注目していきたいと思います。
※元の情報や詳細については、厚生労働省の公式資料等をご参照ください。
第1回福祉人材確保専門委員会 資料|厚生労働省