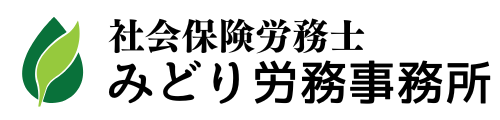派遣の同一労働同一賃金 – 放置リスクとトラブル防止策
「派遣労働者の同一労働同一賃金」に関するセミナーで講師を務めました。
「同一労働同一賃金」制度自体は、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差解消を目的としており、中小企業にも2021年から既に適用されています。派遣労働者に関しては、その適用が早く、大企業・中小企業を問わず2020年4月からスタートしています。
しかしながら、法施行からすでに数年が経過した今でも、「派遣元」・「派遣先」の双方で「対応はしているつもりだが、これで本当に正しいのか」「複雑でどこまで手を付ければいいか分からない」といった疑問や不安の声が絶えません。
この制度対応が後回しになったり、曖昧なまま放置されてしまうケースも残念ながら見受けられます。
「派遣」特有のトラブルの火種を放置していませんか?
ご存知の通り、派遣労働者の同一労働同一賃金には「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」という二つの対応ルートがあり、どちらを採用するかによって派遣元・派遣先それぞれに求められる対応が異なります。
特に以下のリスクは、今こそ注意が必要です。
- 派遣労働者からの説明要求の増加 自身の待遇が正社員や他の非正規社員と比べて不合理ではないか、根拠を求められる場面は確実に増えています。 **「なぜこの手当は支給されないのか」「協定方式の賃金テーブルの根拠は」**など、明確に説明できない待遇差は、不信感を生み、大きなトラブルのきっかけになります。
- 労働局の監督指導の本格化 制度施行初期の啓発フェーズから、今後は労働局による調査や是正指導がより本格化されることが予想されます。 未対応や不備が指摘された場合、是正に要する時間やコストは計り知れません。最悪の場合、高額な賠償請求など思わぬ労務トラブルに発展しかねません。
いますぐ確認すべきポイント(派遣元・派遣先共通)
派遣労働者の待遇を見直す上で、特にリスクが高く、優先的に点検すべき項目があります。
- 待遇差の「根拠」を明文化していますか? 「感覚的に」や「慣例で」といった説明では通用しません。正社員と派遣労働者の手当、賞与、福利厚生などの待遇差について、「職務内容」「責任の程度」「配置の変更の範囲」といった要素に基づき、合理的な理由があることを明確に整理・文書化しましょう。
- 通勤手当や精勤手当など「不合理」と判断されやすい項目は? 過去の最高裁判例でも、一部の手当(家族手当、通勤手当、精勤手当など)について、非正規社員への不支給が「不合理」と判断された事例があります。こうした判例でリスクが顕在化している項目から優先的に点検・見直しを行うのが、トラブル回避の近道です。
- 労使協定方式の場合:賃金テーブルは適切ですか? 労使協定方式を選択している派遣元様は、職種に応じた一般の労働者の賃金水準を適切に満たしているか、またその根拠となる資料をいつでも提示できるか確認が必要です。
当事務所のサポートについて
当事務所でも、派遣元・派遣先の立場に応じた制度の簡易診断から、労使協定の策定支援、複雑な制度設計のご相談まで対応可能です。
働き方改革、そして人手不足の時代において、適正な待遇は優秀な人材の確保と定着に直結します。
今こそ、派遣労働者の待遇を改めて見直し、リスクを避けながら、働く人との信頼関係を築ける制度づくりを一緒に進めていきましょう。
まずはお気軽にご相談ください。